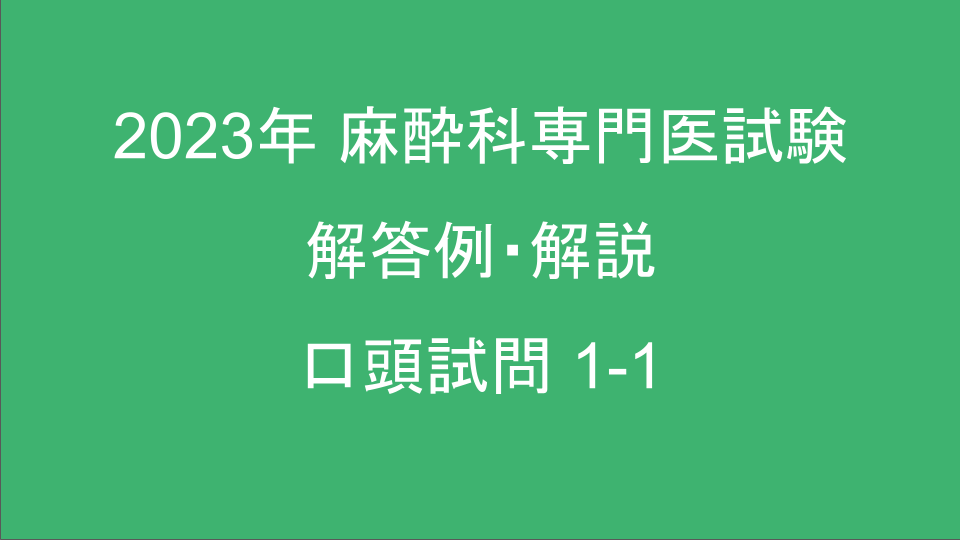2023年の麻酔科専門医試験 口頭試問の過去問解説を行っていきます。
公式解答は発表されておりませんので間違い箇所がございましたらお問い合わせ欄もしくはTwitterのDMより指摘いただければ助かります。
日本麻酔科学会公開の専門医試験過去問はHPから御覧ください(日本麻酔科学会HP)。
DL方法:ログイン⇨認定施設申請⇨過去問(口頭試問)
問1 解答例
1) ASA-PS(ASA Physical Status)分類
ASA-PS 5(さらに手術が緊急であることから 5E とすることが多い)
2) Child-Turcotte-Pugh(チャイルド・ターコット・ピュー)分類
Child-Pugh C
解説
1) ASA-PS(ASA Physical Status)分類
本症例は,急性肝不全で肝移植をしなければ救命が困難な状態であり,いわゆる「瀕死状態(moribund)」に相当するため,ASA-PS 5(さらに手術が緊急であることから 5E とすることが多い)と判断できます。
緊急手術かの判断は患者の治療の遅れが生命または身体への脅威の著しい増加をもたらす場合に存在すると定義されるため、明日の予定ですがEをつけてもいいと思われます。
2) Child-Turcotte-Pugh(チャイルド・ターコット・ピュー)分類
Child-Pugh は以下5項目(総ビリルビン・アルブミン・PT(あるいはPT-INR)・腹水・脳症)を1~3点でスコア化し,合計点でA(5~6点)・B(7~9点)・C(10~15点)に区分します。
総ビリルビン(T-Bil 12.9 mg/dL) → 3点(>3 mg/dL)
アルブミン(Alb 2.1 g/dL) → 3点(<2.8 g/dL)
PT-INR(4.61) → 3点(INR>2.3)
腹水 → 不明(1~3点)
肝性脳症(意識混濁あり) → 3点(重度)
以上を合計すると13~15点となり,Child-Pugh C となります。
問2 解答例
以下から6つ以上を回答
1. 重症肝障害(Child–Pugh C)、人工呼吸器管理中であり、極めて悪い全身状態
2.肝性脳症(意識混濁)による中枢神経系評価の困難:意識レベルが低下しており,術後の神経学的評価・鎮静深度の判断などが難しくなる。
3.著明な凝固障害(PT-INR 4.61 など)。肝合成能の低下により凝固因子が不足しており,大量出血や止血困難のリスクが高い。
4.繰り返す炎症により腹腔内が癒着している可能性。
5.低アルブミン血症(Alb 2.1 g/dL)・低栄養状態:低コロイド浸透圧や薬物の蛋白結合率低下,創傷治癒遅延などのリスクを伴う。
6.感染リスク・敗血症の可能性;白血球数が 20,800/μL と著増しており,既往に胆道感染症を反復している背景もあるため,周術期の感染管理が重要となる。
7.緊急手術(救命目的の肝移植)であり十分な術前管理・改善が困難:血液浄化療法や交換輸血などを施行してはいるが,予定手術とは異なり術前に十分な全身状態の最適化を図る時間がない。
8.高カリウム血症:致死的不整脈の原因となるため、電解質の補正に努めます。
問3 解答例
FFPおよびクリオプレシピテートの投与を行います。
肝不全に伴い、凝固因子の著明な低下を示唆し,血液粘弾性試験でも立ち上がり(Rや CT)の遅延、α 角や最大凝固能(MCF/MA)の低下がみられます。
新鮮凍結血漿(FFP) は広範な凝固因子を補充でき,PT/INR の改善が期待されます。
フィブリノゲン製剤 で直接フィブリノゲンを補充することで,早期に凝固力(クロット形成・維持能)を改善できます。
補足:他の製剤を優先しない理由
・濃厚赤血球
– Hb 10.4 g/dL 程度であれば,まずは凝固能補正が優先されるケースが多い。
– 大出血や更なる貧血進行があれば追加を検討。
・血小板濃厚液
– 術前の血小板数が 13~14 万/μL 程度(おおむね 10 万/μL 超)であれば,まずはフィブリノゲンや凝固因子を補正してから必要に応じて追加する。
・プロトロンビン複合体製剤(PCC)
– ビタミンK 依存性因子(II, VII, IX, X)の迅速補正に有用。
– ただし フィブリノゲンを含まない ため,本症例のように「凝固因子全般+フィブリノゲン」が同時に低下している場合は FFP+フィブリノゲン製剤 の組み合わせがより一般的。
問4 解答例
血液粘弾性試験結果から線溶系の亢進状態と考えられ, 凝固能低下が継続しているので、トラネキサム酸、FFPを投与します。
どの凝固因子や血小板が主に不足しているかを評価し、必要な製剤を追加オーダーし、適宜投与します。
補足:
1:主要な不足因子ごとの対応
・フィブリノゲン低下が顕著な場合→Cryoprecipitateやフィブリノゲン製剤を追加。
・血小板の MA 低下が大きい場合→血小板製剤を追加。
・FFP が乏しい状況下で PT-INR が高度に延長している場合 →PCC(プロトロンビン複合体製剤)を検討する。
・過剰線溶がある場合 →トラネキサム酸などの使用を検討する。
2:凝固環境を最適化する。(本症例は正常範囲のため補正不要)
・体温管理を徹底する。
・アシドーシス補正を行う。
・Ca補正
問5 解答例
1:再灌流1分後からテント状T波
2:再灌流2分後からP波平坦化、QRS延長
3:再灌流4分後から徐脈化、sine wave化
知識:高カリウム血症に伴う心電図変化の主な4つのポイント
・T波の尖鋭化(テント状T波)
– 高カリウム血症初期~中等度では、T波が高くとがった形状(テント状)になる。
・P波振幅の低下・消失
– 血清カリウム濃度がさらに上昇すると、P波が平坦化し、やがて消失することがある。
– PR間隔の延長も伴うことが多い。
・QRSの延長
– 重度高カリウム血症では、QRSが広くなる。
– P波消失と重なり、波形が“ワイド”に見えてくる。
・洞停止や徐脈化、最重症でsine wave化
– さらに進行すると、徐脈化したり洞停止や房室ブロックを引き起こすこともある。
– 最重症ではQRSとT波が融合し、“sine wave”様の波形になり、そのまま心静止または粗大な心室細動に移行しうる。
問6 解答例
1: 高カリウム血症に対し、心筋保護のためのカルシウム製剤の投与、K濃度を下げるためのGI療法の開始、炭酸水素ナトリウムの投与をします。
2: 高カリウム血症に対し、赤血球輸血の一時中断します。
3: 血圧低下の原因検索のため、術野で出血、圧迫がないか、CVP、TEE等各種モニター値の確認をします。
4: 血圧低下のため、カリウムフリー輸液の急速投与、昇圧薬としてフェニレフリンやノルアドレナリン等の投与 , 心機能低下が見られる場合にはドパミンやドブタミンなどの投与も考慮します。
問7 解答例
1:再灌流前に予め血中K濃度を低下させておく。
2:灌流中に血液ガス測定でK値を測定し、必要があればGI療法等でK値補正を行う。
補足(麻酔科医が行うことではないことも含まれます)
- 再潅流時の高カリウム血症を予防する工夫
・移植肝を再潅流する前に十分なフラッシュ(生理食塩水や低K+の溶液など)を行う。
・移植臓器内に蓄積したカリウムや酸性代謝産物を洗い流す。 - 背景となるメカニズム
・肝移植では、冷却保存液や組織内にカリウムが蓄積していることがある。
・再潅流の瞬間に血中へ一気に放出され、高カリウム血症を引き起こす可能性がある。
・事前に移植肝を充分に灌流することで、組織にたまったカリウムを除去・希釈し、高カリウム血症のリスクを低減できる。 - その他の代表的な予防策
・再潅流直前にインスリン+ブドウ糖を投与する。→ 受容者(レシピエント)の血中K+を低下させておく。
・腎機能不良などで高カリウムになりやすい場合 → 事前に血液透析/血液ろ過を考慮する。
・アシドーシス・体温・Ca補正など、周辺環境を最適化しておく。 - まとめ
・再潅流前に高K+が血中や臓器内に溜まらないようにするための具体策を挙げることが重要。
・適切な事前管理によって 高カリウム血症のリスクを最小限に抑えることが可能です。
問8 解答例
バンピング圧が低下しておらず換気可能です。
また病院内の中央配管からの酸素供給が仮に停止してたとしても、ボンベ内は 3.4Lx7.8 (MPa) = 265L程度の酸素が存在し、新鮮ガスとしての使用量は0.5L/分のため、安全係数 0.8 を考慮して計算すると265×0.8/0.5=424分。手術終了までは十分に動作可能です。
問9 解答例
(1) 手術継続の可否を患者状態とリスクから外科医と相談し方針決定する。
(2) 手術室や麻酔器など設備の安全性・非常電源・物資を再点検を指示する。
(3) 院内指揮系統への連絡と情報共有を指示します。
(4) スタッフ・患者の安全確保と余震対策を指示します。
補足
【1】手術の継続可否の判断と安全確保
手術の進行状況・患者の状態を即時に再評価
現在「洗浄・ドレーン挿入後に閉創へ移行」という段階で、1時間程度で終了見込み。
患者の循環動態・呼吸状態が安定しているかを確認し、続行可能と判断した場合は速やかに手術を完了させる。
危険が大きいと判断した場合は、一時的な創処置(応急的なドレーンやガーゼ)で中断し、安全な環境へ移動を検討する。
【2】設備の安全性・非常時物資の確認
手術室の構造的安全性・機器類の点検
外回り看護師等が速やかに天井部や照明の破損、酸素配管や麻酔器の転倒リスクなどを再チェック。
非常電源・麻酔器のガス圧・ボンベ残圧を再確認し、1時間継続に十分な量があるかを把握する。
必要があれば、予備の酸素ボンベや非常時物資(止血用資材など)の確保を指示。
【3】院内連絡・情報収集
院内の災害対策本部または指揮系統への連絡
病院全体の被害状況やライフライン(電気・水道・医療ガス)の状態を早急に確認する。
外科医師や看護師は、現場の状況・患者の状態を報告し、緊急度の高い他の症例への対応可否なども情報共有。
必要に応じて、追加スタッフ(予備人員)の派遣を依頼。
【4】スタッフの安全と二次災害への備え
余震に備えた安全対策・避難経路の確認
手術室周囲の落下物の危険や緊急時の避難ルートを再度周知し、スタッフ自身の安全確保を徹底する。
万が一、再度の大きな揺れが発生した際の患者の保護(必要最低限の固定)や機器の固定を確認。
スタッフの交代要員や疲労度にも配慮し、長期化に備える。