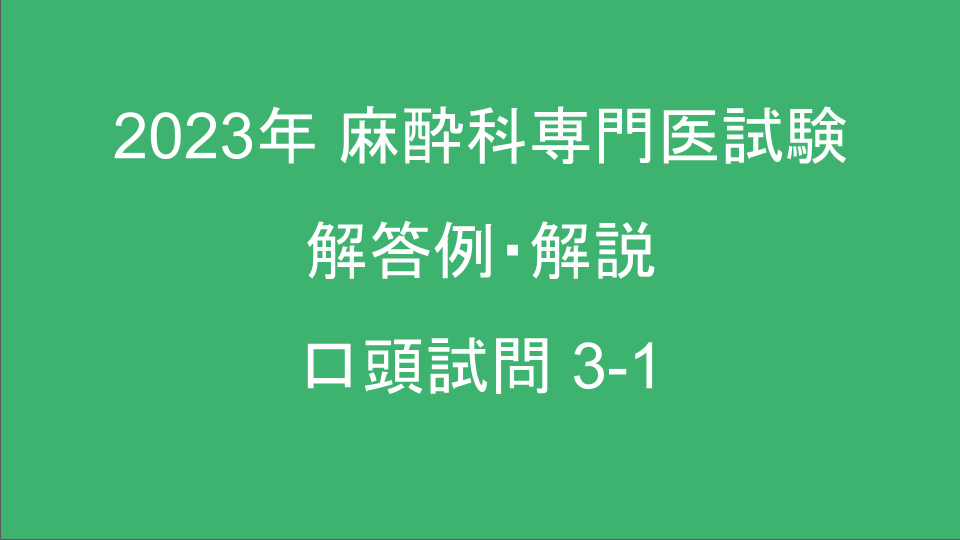2023年の麻酔科専門医試験 口頭試問の過去問解説を行っていきます。
公式解答は発表されておりませんので間違い箇所がございましたらお問い合わせ欄もしくはTwitterのDMより指摘いただければ助かります。
日本麻酔科学会公開の専門医試験過去問はHPから御覧ください(日本麻酔科学会HP)。
DL方法:ログイン⇨認定施設申請⇨過去問(口頭試問)
問1 解答例
心電図所見:デルタ波あり
胸部CT:気腫状変化, ブラあり
問2 解答例
鑑別:抗菌薬あるいは筋弛緩薬によるアナフィラキシーショック, ブラ破裂による緊張性気胸、肺血栓塞栓症
できること:視診にて顔面~前胸部に紅斑があればアナフィラキシー、胸郭の動きの左右差があれば緊張性気胸の可能性、聴診にてアナフィラキシーであれば気管狭窄音が聞こえ、緊張性気胸であれば呼吸音の左右差がある。また、TEEにて肺塞栓の確認、TTEにて気胸の確認、胸部X線写真にて気胸の確認を行います。
問3 解答例
緊張性気胸ではない。
肺エコーで胸膜、Blineが確認できます。(もし動画ならsliding signが見られるはずです)
胸部X線でも明らかな気胸を示唆する胸膜線はなく、肺野の透過性の亢進も見られません。
解説:気胸の診断における所見のまとめ
1. 胸部X線写真の所見
胸膜線の確認:
肺の虚脱により、肺の縁(胸膜線)が明瞭に描出される。胸膜線の外側にはガスが貯留し、透過性が増加している(黒く見える)。
肺野の透過性の増加:
気胸側の肺野で肺紋理が消失し、透過性が増加。特に大きな気胸では特徴が顕著。
2. 胸部エコーの所見
Lung Slidingの消失:
通常の呼吸に伴う肺表面の動き(Lung Sliding)が確認されず、気胸を示唆。
Barcode Sign(Stratosphere Sign):
Mモードで平行な線のみが描出され、正常なSea Shore Signが消失。
Lung Pointの確認:
正常な肺と虚脱した肺の境界を示す所見で、気胸の存在と範囲を特定。
Bラインの消失:
通常見られる肺表面からの垂直な反射線(Bライン)が消失し、Aライン(水平線)のみが観察される。
問4 解答例
被疑薬を直ちに中止
輸液の急速投与
アドレナリン0.1mgを緩徐に静注、皮下注なら0.3mg。血圧や心拍数の改善が不十分なら,持続静注(0.01~0.1 μg/kg/min)に移行
抗ヒスタミン薬、ステロイドの投与
昇圧剤の投与、頭低位
問5 解答例
電気ショック (同期) による除細動
アデノシンの急速投与
急速補液、100%酸素の投与
解説:一般的な発作性上室性頻拍(PSVT)の対応まとめ
1. 初期評価と準備
バイタルサインの評価:
・血圧、心拍数、酸素飽和度の測定。
・症状(胸痛、めまい、意識障害など)の確認。
モニタリング:
・心電図(ECG)モニタを装着し、リズムを記録。
・酸素投与を必要に応じて行う。
2. 安定している患者への対応
迷走神経刺激法(迷走神経反射誘発法):
・バルサルバ法: 深呼吸後に腹圧をかける。
・頸動脈洞マッサージ: 頸動脈洞を軽くマッサージ(禁忌:頸動脈硬化の疑いがある場合)。
・その他:顔面への冷水刺激(寒冷反射の利用)。
薬物療法:
迷走神経刺激法が効果がない場合、以下を選択。
・アデノシン: 静注(短時間作用型で安全性が高い)。
・カルシウム拮抗薬: ベラパミル、ジルチアゼム(禁忌:重症心不全、低血圧)。
・β遮断薬: メトプロロール(禁忌:重症喘息、低血圧)。
3. 不安定な患者への対応
症状:
・血圧低下、意識障害、胸痛、重度の呼吸困難がある場合。
対応:
・直流(DC)カルディオバージョン: 緊急の電気的除細動(50~100Jから開始)。
・必要に応じて酸素投与や輸液を行い、循環動態を安定させる。
4. 根本治療(再発予防)
慢性管理:
・再発を防ぐため、β遮断薬やカルシウム拮抗薬を内服。
・発作が頻回の場合、カテーテルアブレーションを検討。
教育:
・患者に発作時の対処法(迷走神経刺激法)を指導。
・トリガー(カフェイン、アルコール、ストレス)の回避を促す。
まとめ
PSVTの対応では、安定した患者には迷走神経刺激法を試み、必要に応じて薬物療法を追加。不安定な場合は速やかにDCカルディオバージョンを行い、再発防止のための治療計画を立てることが重要です。
今回の場合は術中であり、バイタルが不安定なPSVTですので、DCが1st choiceとなります。
問6 解答例
麻酔科の〇〇と申します。今回,手術の最初の段階で使用した薬剤によって,強いアレルギー反応(アナフィラキシー)が起こり,血圧が急激に低下しました。すぐにアドレナリンなどのお薬を投与して,現在は血圧や脈拍も回復し,症状は落ち着いています。ただし再発のリスクもあるため,集中的に監視できるICUで治療を続けます。
アナフィラキシーは原因となる薬剤や物質を特定することが重要です。今後は原因検査をし,次回以降の手術や治療で同じような事が起きないように備えます。ご家族の方には詳しい検査内容や経過を随時ご説明していきますので,ご安心ください。
解説
アナフィラキシーの定義や重篤性を家族に理解してもらうことが大切です。
術後にICU管理が必要な理由と,原因検索を行う意義(再発防止)を説明する。
また,今後手術や検査時に「今回アナフィラキシーを起こした」旨を必ず申告するよう促すのも大事なポイントです。