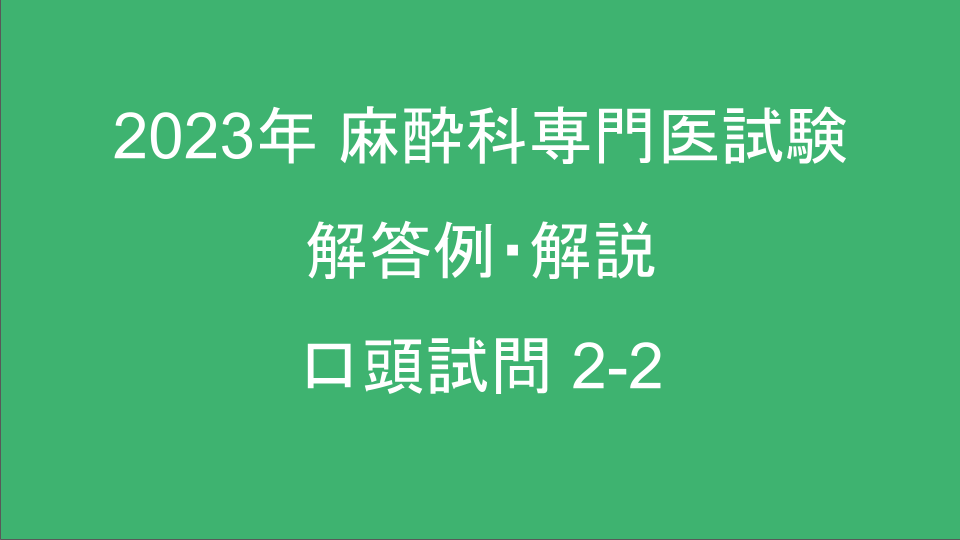2023年の麻酔科専門医試験 口頭試問の過去問解説を行っていきます。
公式解答は発表されておりませんので間違い箇所がございましたらお問い合わせ欄もしくはTwitterのDMより指摘いただければ助かります。
日本麻酔科学会公開の専門医試験過去問はHPから御覧ください(日本麻酔科学会HP)。
DL方法:ログイン⇨認定施設申請⇨過去問(口頭試問)
問1 解答例
誤っている点:
SGLT2阻害薬を当日まで内服している。
誤っている理由:
術前3日前には中止するべき
解説
SGLT2阻害薬は血糖降下作用のほか,「術中・術後の脱水やケトアシドーシス」リスクを高めると報告されている。とくに長時間絶食や侵襲の大きい手術では,術前3日前には中止が推奨される。
問2 解答例
ヘパリン持続静注は、硬膜外麻酔の6-8時間程度前に中止し、入室時にACTを測定する。
術後経口摂取可能になるまでヘパリン持続静注が再開されると思われますが, 硬膜外カテーテル抜去前の2~4時間前に中止する。抜去後もヘパリン再開までは2時間程度空けます。穿刺や抜去の時期を誤ると,硬膜外血腫による神経麻痺のリスクが高まるので注意します。手技が難しそうな場合も出血のリスクが高まるため、早期に中止を検討します。
問3 解答例
循環血液量の十分な評価と管理
酸化ストレス・乳酸の流入、アシドーシスへの対策
カリウムなどの電解質異常への対策
血圧の連続モニタリングと昇圧薬の準備
解説
循環血液量の十分な評価と管理
遮断解除で下半身への血流が急に再開→血管床が拡張して相対的に還流血液量が不足し,急激な血圧低下を起こす。事前に輸液や輸血で血管内ボリュームを確保する。
酸化ストレス・乳酸の流入への対策
末梢組織に貯留していた乳酸やカリウムが一気に流入し,代謝性アシドーシスや高K血症を起こすリスク。徐々にクランプをリリースし,併せて重炭酸ナトリウム投与や換気設定調整を行う。
血圧の連続モニタリングと昇圧薬の準備
急な低血圧に対処するため,ノルアドレナリンやフェニレフリンなどの昇圧薬を事前に準備。持続投与やボーラス投与で素早く対応。
大動脈弁疾患や冠動脈疾患があれば,再灌流に伴う急激な前負荷/後負荷変動で心不全や虚血を誘発する。心エコー(TEE)などで心機能を評価しつつ慎重に解除する。
問4 解答例
手が空いている麻酔科医を呼び、必要なサポートを依頼します。患者の体温管理のため、加温を実施します。輸血が必要となる可能性を考慮し、輸血在庫を確認し、不足している場合は手術室に取り寄せます。また、採血を行い、血液ガス、血算、凝固機能の評価を実施し、トロンボエラストグラムを用いた追加の検査も行います。
問5 解答例
Rの延長とMAの低下が認められ、凝固因子の低下が疑われるため、FFPやクリオプレシピテートの投与を行います。
問6 解答例
低体温による麻酔薬代謝遅延
筋弛緩残存(筋弛緩拮抗が不十分)
鎮静薬の残存・蓄積
オピオイドの過剰投与/蓄積
中枢神経系イベント(脳梗塞、脳出血)
問7 解答例
硬膜穿刺後頭痛 (PDPH)
解説
PDPHの主な特徴
頭痛の性質:前屈位や立位で悪化し、仰臥位で軽減することが多い。
伴う症状:悪心、嘔吐、頸部硬直、視覚や聴覚異常を伴うこともあります。
発症時期:通常、穿刺後24〜48時間以内に発症しますが、遅れて出現する場合もあります。
治療
保存的治療(安静、十分な水分摂取、カフェインの投与)
効果が不十分な場合はブラッドパッチ(患者自身の血液を硬膜外腔に注入する治療)が行われることが多いです。
問8 解答例
麻酔を担当させて頂きました麻酔科〇〇です。背中に麻酔の針を入れたときに,まれに脊髄液が少し漏れてしまうことがあります。治療としては、水分摂取とカフェイン、鎮痛薬の摂取をし、数日~2週間程度経過観察します。それでも症状が続く場合,“自分の血液を少し採って背中に注射する”という方法(自家血パッチ)で頭痛が改善することが多いです。
問9 解答例
穿刺部位
患者の症状を最も改善しやすいレベル(通常は穿刺部位と同じか1椎間ほど尾側)で,硬膜外腔へ穿刺する。
採血方法
滅菌操作の下,静脈血を20 mL程度(症状や患者体格により調整)採血し,すぐに同じ針から硬膜外腔へ注入する。
採血と注入を同時に行えるように連結チューブを使う場合もある。
自家血注入量
まずは10–15 mL程度から慎重に注入し,患者に腰や背中の圧迫感・痛みがないか確認しながら追加する。最大20–30 mL程度まで。
注入後は30分程度仰臥位または安静にして血液が凝固・線維性プラグを形成するのを待つ。
まとめ
本症例のポイントは以下です。
術前内服薬(SGLT2阻害薬など)の中止タイミング
大血管手術における硬膜外麻酔と抗凝固療法の両立
大動脈遮断解除時の循環動態変動(血圧低下,酸性代謝物,K↑)に対する管理
大量出血時のTeg/ROTEMを用いた適切な製剤投与
術後の低体温・薬物残存・代謝異常などによる覚醒遅延の鑑別
硬膜穿刺後頭痛(PDPH)の診断と自家血パッチの手技
どれも頻出ジャンルなので何度も確認しましょう。