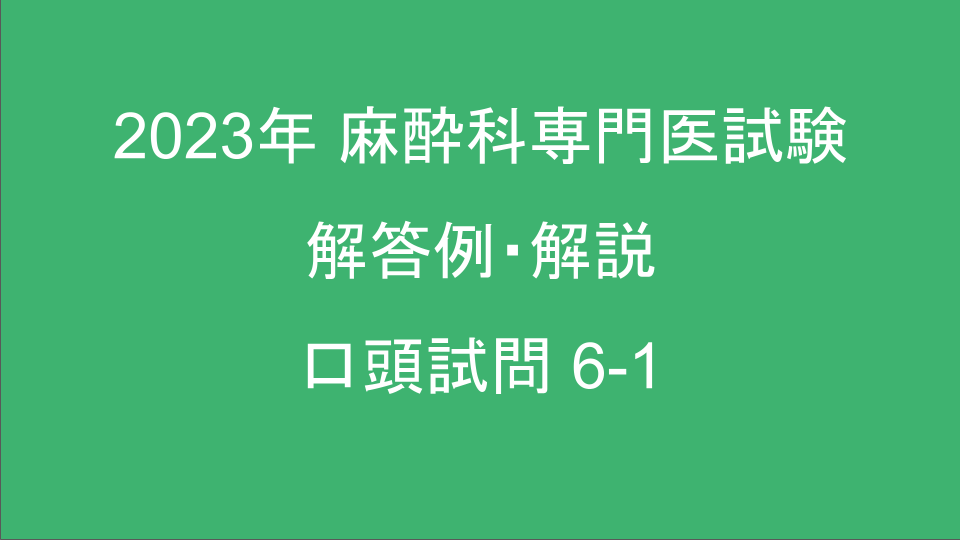2023年の麻酔科専門医試験 口頭試問の過去問解説を行っていきます。
公式解答は発表されておりませんので間違い箇所がございましたらお問い合わせ欄もしくはTwitterのDMより指摘いただければ助かります。
日本麻酔科学会公開の専門医試験過去問はHPから御覧ください(日本麻酔科学会HP)。
DL方法:ログイン⇨認定施設申請⇨過去問(口頭試問)
問1 解答例
・目標とする筋弛緩レベル
- 一般的な開腹手術や腹腔鏡手術では中等度の筋弛緩を保つことが多い
- 具体的には TOF カウント 1~2 程度を目安にし、手術操作中の不動化を確保する
・筋弛緩モニター(尺骨神経刺激による筋電図)での確認方法
- TOF(Train-of-Four)刺激時の twitch 数を観察
- 例えば TOF 刺激で 1~2 の状態を保つように筋弛緩薬を追加投与し管理する
解説
目標とする筋弛緩レベルについて
手術の種類や術式によって異なりますが、以下のように目標レベルを設定します。
・浅い筋弛緩: TOF比(Train-of-Four ratio)が0.9以上(覚醒時の目標)。
・中等度筋弛緩: TOF反応が1~2回(腹腔鏡手術など、適度な筋弛緩が必要な場合)。
・深い筋弛緩: TOF反応が0回、PTC(Post-Tetanic Count)が1~5回(内視鏡下手術や狭い手術部位の場合)。
・開腹や腹腔鏡など術野が広範囲の場合、ある程度の筋弛緩深度を維持しないと体動や筋緊張により術野が不良になる
・尺骨神経刺激では母指内転筋反応が比較的正確に反映される
・深すぎる筋弛緩は過剰投与・覚醒遅延につながり、浅すぎると術野確保が困難になるため、モニターを用いた適切な投与調整が重要
問2 解答例
- TOF カウントが 4 になり、かつ TOF ratio が 0.9 以上に自然回復するまで待機
- その上で臨床的確認(頭挙上 、握力、呼吸状態など)を行い抜管
問3 解答例
・(1) 吸気/呼気ホースと麻酔器本体、マスク、フィルタなどの接続部
・(2) ベローズやそのカバー周辺
・(3) CO₂吸収缶とそのパッキン部分
・(4) リザーバーバッグとそのコネクタ
・(5) APL弁(呼気調節弁)周辺
解説
・始業点検不合格時は、ホース類やバッグなど接合部の緩みや破損、ベローズカバーのずれが原因となりやすい
・CO₂吸収缶の装着が不十分だと吸収缶まわりのパッキンからリークが生じる
・麻酔器上部(バイパス流路や蒸発器など)に問題がある場合もあるが、問題文では医療ガス配管は正しいとあるため、機器周辺・回路接合部のリークが想定される
問4 解答例
・(1) 適切な輸液負荷
・(2) ノルアドレナリン持続投与
・(3) バソプレシン持続投与
問5 解答例
・(1) 血液ガスで電解質のチェック
・(2) TTE/TEEで心臓壁運動のチェック
・(3) 12誘導心電図
・(4) DCや抗不整脈薬の準備
問6 解答例
・呼吸管理(3つ)
(1) 肺保護換気(低一回換気量+適度な PEEP)を行う
(2) 術後鎮痛の程度や覚醒レベルをみながら、早期離脱か持続人工呼吸かを判断
(3) 定期的な血液ガス分析と胸部画像評価で呼吸状態(肺炎・無気肺・ARDS など)を観察
・循環管理(3つ)
(1) ショックバイタルに陥らないように、ノルアドレナリンなどの昇圧薬を用いて平均血圧確保(>65 mmHg 程度)
(2) 充分な輸液管理と必要に応じた血液製剤投与(出血や凝固状態を評価)
(3) 敗血症に対して適切な抗菌薬、ドレーンでの治療を行い、末梢血管の拡張を改善する。
問7 解答例
CVカテが動脈内留置されている可能性。
問8 解答例
・(1) 抜去前に血圧波形をモニタで確認(圧トランスデューサにつないで動脈波形が出るか)
・(2) カテーテルから採血して血液ガス分析(PO₂・PCO₂・pH が動脈血と一致する)
・(3) エコーガイド下での穿刺部位とカテーテル先端走行を追加評価(超音波検査による確認)