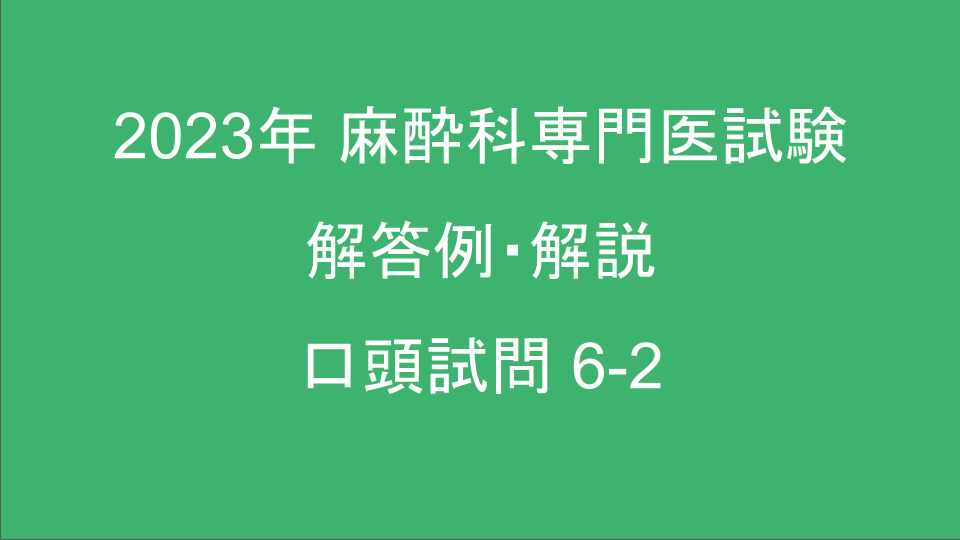2023年の麻酔科専門医試験 口頭試問の過去問解説を行っていきます。
公式解答は発表されておりませんので間違い箇所がございましたらお問い合わせ欄もしくはTwitterのDMより指摘いただければ助かります。
日本麻酔科学会公開の専門医試験過去問はHPから御覧ください(日本麻酔科学会HP)。
DL方法:ログイン⇨認定施設申請⇨過去問(口頭試問)
問1 解答例
(1) 出生児の状態
(2) 睡眠時無呼吸、いびきの有無
(3) 現在の風邪症状
(4) 喘息の既往、家族の喫煙歴
解説
-小児の「かぜ」の病み上がりは気道過敏性が残存し、周術期呼吸合併症が起こりやすい
-一見症状がないようでも、「寝入りばなに咳が出る」「運動量が増えると息苦しそう」など詳細問診が重要
-麻酔前に呼吸状態が十分に回復していないと、術中・術後に気道反応性亢進や喉頭痙攣、気管支痙攣などのリスクが高まります
問2 解答例
○○くんは 2~3週間前にかぜをひき、今は症状は治まっていますが、気道がまだ敏感になっている可能性があります。麻酔を行う場合、気管にチューブを入れてしっかり呼吸を管理します。しかし、最近のかぜの影響で痰が出やすかったり気道が狭くなりやすかったりして、術中や術後に咳き込みや呼吸が苦しくなるリスクがあります。もし手術を予定通り行うとすれば、こちらで丁寧に呼吸状態を管理して、必要があれば気管支拡張薬や痰を出しやすくするお薬などを使ってリスクを軽減いたします。手術を延期する選択もあり得ますが、外科的なタイミングを考えると今が最適ということであれば、周術期の呼吸合併症のリスクをなるべく抑えるよう全力で対策いたします。
問3 解答例
-(1) 吸入酸素濃度を速やかに 100% に変更
-(2) 気道確保の補助具を利用(経口エアウェイなど)
-(3) マスクを再確認し、顎先挙上や下顎挙上法で気道を確保
-(4) 必要に応じてサクションや気道内分泌物の吸引
-(5) 追加のヘルプを呼び、2人法での換気、気道確保(LMAや挿管)を検討
問4 解答例
チューブ選択:4.5mmカフ無しチューブ or 4.0mmマイクロカフありチューブ
固定長:12~14cm程度
解説
-「(年齢/4) + 4」はカフなしチューブサイズの目安で、2歳なら(2/4)+4=4.5 mm となる
-しかしカフありチューブの場合、1~0.5 mm 小さいサイズを選択することが多い
-チューブの固定長は年齢や身長から推定式があるが、実際には聴診やETCO₂波形などで再調整
-本症例では 4.0 mm カフ付きチューブが使用され、その場合 13~14 cm 程度が口唇固定長の目安
-固定長はおおよそ「年齢 × 1 + 12」程度で推定すると 14 cm)
問5 解答例
仙骨裂孔は左右の上後腸骨棘と正三角形を形成するためランドマークにして穿刺します。解剖学的には、仙骨裂孔は仙骨後面の下部にある逆U字型の隙間で、尾骨を正中とするラインで左右の仙骨角の間にあります。
問6 解答例
-(1) 引圧確認・血液や脳脊髄液の逆流がないか確認する(血管穿刺やくも膜下腔穿刺防止)
-(2) 少量ずつ分割投与し、抵抗変化や患児の状態(心拍変化、注入部の膨隆がないか)確認
-(3) 注入抵抗が異常に高くないか確認(チップ折損や異所性注入防止)
問7 解答例
-(1) 分泌物による気管支閉塞。
-鑑別方法: 両肺聴診で呼吸音の左右差、肺雑音ないか確認。
-対処法: 気管内吸引し、SpO₂や ETCO₂ の改善を確認
-(2) 気管支挿管。
-鑑別方法: 両肺聴診で呼吸音の左右差、気管チューブ挿管深度の確認、胸部拡張の左右差
-対処法: チューブを少し引き抜き再固定、SpO₂や ETCO₂ の改善を確認
問8 解答例
(1) 不十分な鎮痛による興奮
-対処法: フェンタニル等で十分な鎮痛を行う。
(2) 残存揮発性麻酔薬による中枢神経系の興奮反応
-対処法: 部分的にプロポフォール投与や、刺激を最小限にする。
解説
-小児の覚醒時興奮はセボフルランで比較的高頻度
-術後痛や環境変化への恐怖が合わさると興奮状態が強くなる
-鎮痛・安心できる声かけや環境づくり、場合によっては軽度鎮静を追加することで安全を確保
-大暴れする場合は転落やカテーテル抜去に注意し、しっかり保護したうえで対応する